「丹後国」の由来
その昔、丹後は丹波の一部でした。
丹波は田庭(タニワ)が変化した呼び名です。
大陸から水稲農法がはいり、その水田=田庭であったのが
国名になったのではないか?と考えられています。
丹波国の歴史は古く、2000年以上昔から中国大陸と
往来があり、独特の文化をもっていました。
生産神の信仰もあり、かの豊受大神の信仰も
ここを発端としていることがわかっています。
大陸からの技術、文化に後押しされた丹波国の力は
強大で、大和朝廷さえもその征服は困難だったようです。
713年(和同6年)4月
丹波から「加佐・余社・中郡・竹野・熊野」の五郡を分け
ここに「丹後国」がつくられたのです。
「府中」の由来
この丹後の中心地は天橋立の根本、
「速石の里」=府中へうつされ、
国府(丹後の政治をする役所)
がおかれました。
大仏建立で有名な聖武天皇によって741年、
丹後国分寺も建てられ、丹後の中心地として
ますます栄えたのです。

(現在の国分寺跡) (日本全国にも府中と名のつく地名が多くありますが、 ほとんど例外なく、国府がおかれた土地です。)
奈良・平安時代になると渡来仏教の寺院もたち
室町時代のなかごろに描かれた画僧雪舟の
「天橋立図」をみてもそのさかんな様子がうかがえます。
しかし、室町後期からは戦乱がつづき、江戸時代と
もなると荒れ果て、天平の宝、国分寺も礎石を
残すだけとなってしまいました。
ただ、美しい天橋立のおかげで訪ねる人は多く
沢山の文人・墨客も数多く滞在していた様子です。
現在は傘松公園を中心とした観光地として
すっかり定着していますが、ほんとうは
かなり古い歴史をもつ地区なんですよ。
府中・丹後の情報をもっと知りたい方は
「丹後郷土資料館」を是非訪ねてください。
ここから眺める天橋立(一文字)も
なかなか魅力的ですよ。
丹後郷土資料館
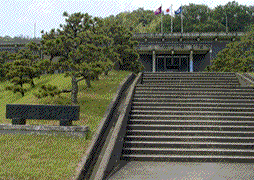
丹後の歴史の事ならココです 展示室観覧料(団体の申し込みについては事前にご連絡下さい)
| 区 分 | 個 人 | 団 体(20人以上) | ●展示休館日 毎週月曜日 年末年始(12/28〜1/4) 臨時休館日 ●開館時間 午前9時〜午後4時30分 |
|
| 普通展示 | 一般 | 200円 | 150円 | |
| 児童・生徒 | 50円 | 40円 | ||
| 特別展示 | 一般 | 250円 | 200円 | |
| 児童・生徒 | 70円 | 50円 | ||
| (但し、65歳以上の方、身体障害者手帳又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者と 介護者、小・中学校等の学校教育活動の場合は無料。) |
||||